「アワビの真珠」館長のブログ188
- Blue East
- 8月17日
- 読了時間: 5分
夏の鳥羽志摩の味覚といえば、第一番はアワビだろうか。9月15日から禁漁期に入るので、そろそろシーズンも終わりにさしかかる。ずいぶん昔の夏の話、広報誌の取材で鳥羽市内の相差の浜を訪ね、海女さんと一緒の船に乗ってアワビ漁に同行したことがあった。前回のゴードン・スミスではないが、その時に海女さんが「ほれ」といって手渡してくれたアワビを丸かじりした。殻を外して肝と外套膜を取り去り、海水で洗って差し出されたアワビの身は堅く引き締まっているが、齧り取って咀嚼するほどに、完熟手前の果実の様な香気を放ちながら軟らかく解けていった。今思えば贅沢な話だ。
さて、前回の補足を少々。ゴードン・スミスが答志島のこととして紹介した『日本書紀』允恭天皇一四年秋の話を要約すると、天皇が淡路島に猟をしたが獲物の姿がない。占うと島の神の祟りで、赤石の海底にある大きな真珠を採って祀れというご託宣。そこで海人を集めて潜らせるが、誰も海底に達することができないのを男狭磯(おさし)という海人が、海底に光る大アワビを見つけ、命がけで引き上げた。そのアワビを裂くと中から「桃の実」のような真珠が出てきた。さっそく神に捧げて天皇は猟を続行したが、男狭磯は過労のあまり息絶えてしまった。気の毒なことだ。
桃の実と聞くと、握り拳大を想像してしまうが、奈良時代には今日のように大きくて瑞々しく甘いモモはない。ヤマモモの大きさとして15ミリから20ミリといったところか。
今日の印象でいうとアワビから真珠の出る確率は低いが、記録あるいは実物として伝わっているものが少しはある。まず、平成6年に養殖研究所大村支所が発行した冊子「研究40年記念誌」の表紙を飾るのが「夜光の名珠」と名付けられたアワビ真珠で、写真解説に高見米一『大村物語』の冒頭部分を引用し、命名の由来を挙げている。
出典を探ると、その昔、大村湾の海面に夜な夜な怪しい光が差し、人々を不安に陥れたことがあった。お殿様は自分の不徳の致すところと自責の念に苛まれ、日夜思い悩む。気の小さい殿様だが、ひとりの勇敢な若者が海に潜って調べてみると光の出所は大きな真珠貝で、貝の中にピンポン玉ほどの真珠が輝いていた、とある。江戸時代の話でピンポン玉はおかしいが、ともかく正体がわかって城下は安堵。取り出した真珠はお殿様に届けられて大村家の宝とされた。光が点滅したのは真珠貝が海底に沈んだり浮き上がったりしたからで、ホタテガイのように貝殻を立てて風に吹かれながら波の上を走っていたから光が動いたなどと説明している。元の話はアワビを想定したものではなかったようだ。
この話は江戸中後期に諸国を遍歴した儒医の橘南谿(なんけい)が著した『東遊記』の「蚌珠」にある新潟県の福島潟の伝承と類似している。これもその昔、月の明るい晩に大きな貝が福島潟の湖面に姿を現し、貝殻を開けることがある。中に見える珠の大きさは拳ほどもあって暁の明星の如く水面にきらめくという。人々は恐れつつ、そっと見守っているだけで大村のように不安を感じる様なことはなかったらしい。
淡水湖の福島潟には現在もイシガイ科の二枚貝が生息しているので、かつては大型のカラスガイから真珠が採れたことでもあったのだろうか。
実は中国の古典に良く似た話がある。明代の『玉芝堂談薈』(だんわい)には1167年の『文昌雑録』からの引用として、湖面に輝きがあるのを見ていると大きな二枚貝が現れて貝殻を開き、片方の殻を船に、もう一方を帆のように立てて湖面を疾走したという話が載せられている。こういう伝承の系統を探ってみるのも面白い。あるいは人の想像力は洋の東西を問わないということか。
話がアワビ真珠から逸れた。
大村湾の「夜光の名珠」は大村家に伝わり、今は三重県南伊勢町の増養殖研究所が保管している。昨年、津市の三重県総合博物館で開催された展覧会に出品されたことは記憶に新しい。美しい緑色と紅色の干渉色が交錯し、印象としてはアワビ真珠の特色を備えている。
明治40年、御木本真珠店が東京勧業博覧会に出品した「軍配扇」にもアワビの真珠が使われている。当時の新聞記事に「上部に嵌めたる三個の中真中の一個は實に稀代の逸品」とある。中央の真珠のサイズは18ミリ×16ミリ×8・5ミリで、左右それぞれは11ミリ前後の扁平形。大村の「夜光の名珠」は15ミリ超と記録されているので、大きさの上では『軍配扇』の真珠が優っていることになる。
記録に残るアワビ真珠はこれも御木本幸吉が秘蔵したと伝わるもので、大正3年の東京大正博覧会に出品された。大王崎沖で採取された貝から採れた24ミリ×19ミリ、重さ264・5グレーンという大物で他を圧倒する。当時のパンフレットによれば「世界第二の真珠」という触れ込みだった。江戸川乱歩が昭和6年の小説『黄金仮面』でこの真珠を「志摩の女王」と名付け、怪盗の餌食にした。
近頃、真珠業界ではアワビ真珠養殖の成功が話題となっている。アワビでは今まで貝殻内面に附着した半径の真珠しかできなかったが、研究を重ねて球形の核を挿入することで、真円真珠の創出が可能となった。その養殖場は大村湾にあり、奇しくも「夜光の名珠」伝説の海域である。事業の発展を願わずにはいられない。
松月清郎 2025年8月17日
写真① 「夜光の名珠」が表紙を飾る
写真② 「軍配扇」 現在は収蔵中
写真③ 上部を飾る3個のアワビ真珠
写真④ 「東京博覧会」向けに作られたパンフレット
写真⑤ クジャクアワビから採取されたアワビ真珠(展示中)





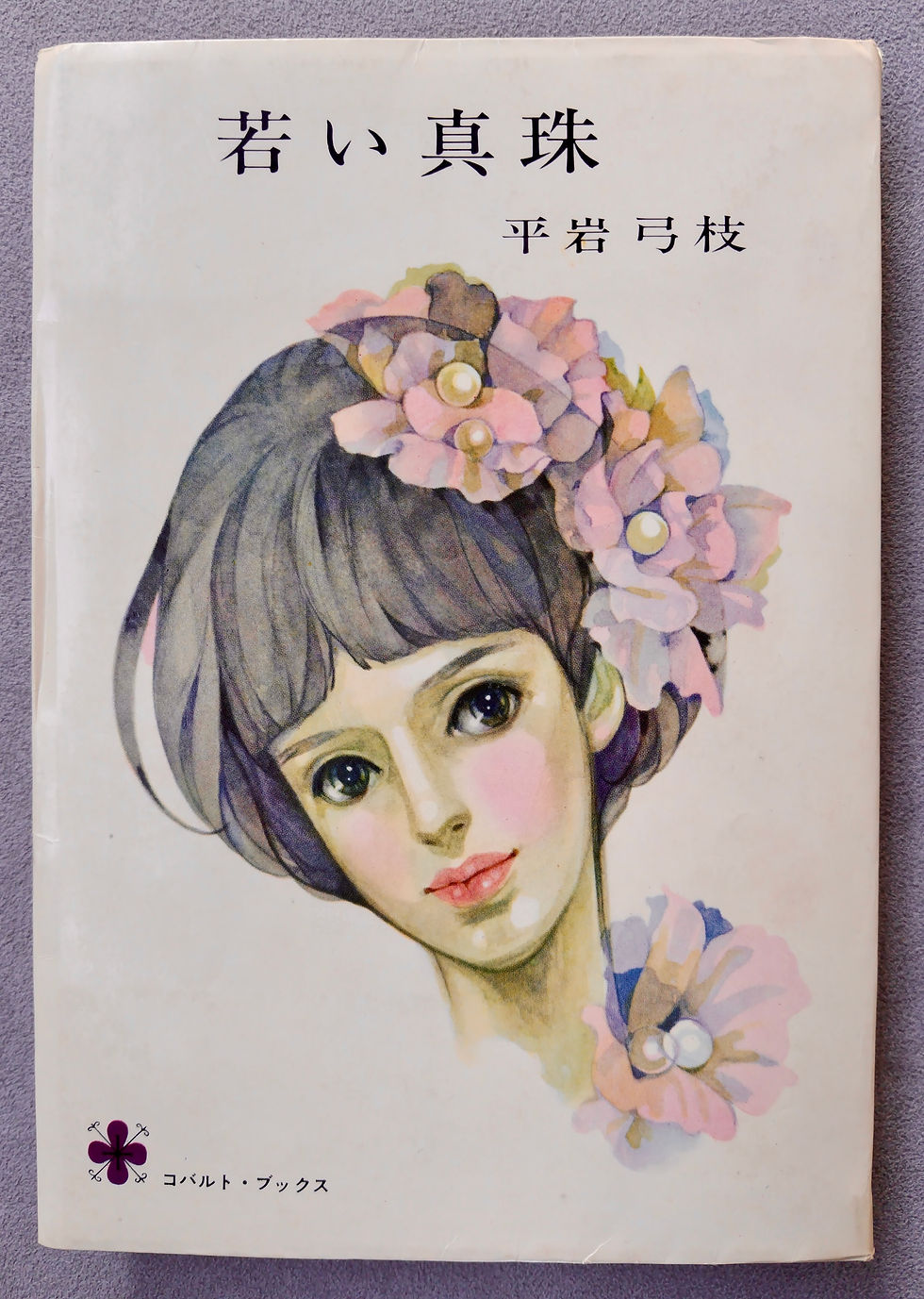


コメント